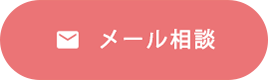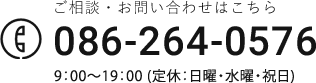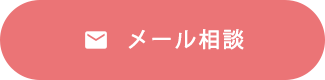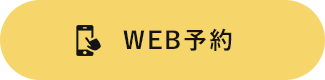漢方で「未病」を防ぐ! 季節の変わり目に負けない感染2025.11.04
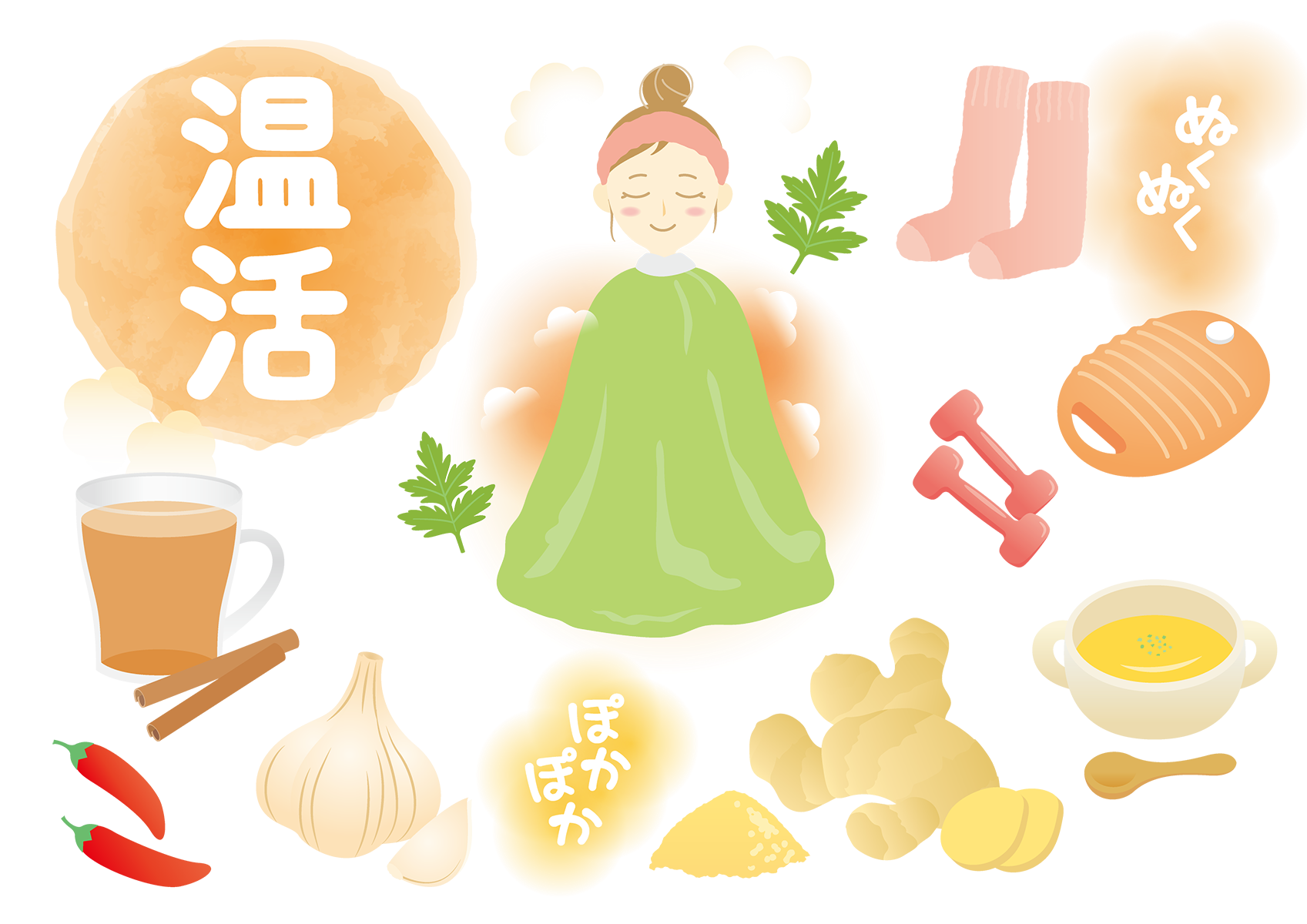
はじめに:なぜ季節の変わり目は体調を崩しやすいのか
「なんだか体調が優れない」「風邪をひきやすい」。季節が移り変わる時期は、そう感じる方が増えるものです。
これは、急激な気温や湿度の変化に体が追いつけず、自律神経や免疫機能のバランスが乱れやすくなるためです。
現代医学では検査に引っかからなくても、病気の一歩手前の状態を漢方では「未病(みびょう)」と呼びます。漢方的な感染症対策とは、この「未病の段階でケアをして、病気を寄せ付けない体づくり」をすることにほかなりません。
私たちが本来持っている病気に打ち勝つ力、つまり「免疫力」を漢方では「正気(せいき)」と呼びます。このコラムでは、「正気」を高める漢方的な養生法をご紹介します。
1. 感染症対策の基本は「正気(免疫力)」を固めること
感染症から体を守るために最も大切なのは、体内の「正気」を充実させておくことです。漢方の考えでは、「正気」が充実していれば、体外から侵入しようとする病気の原因(これを「邪気(じゃき)」と呼びます)を跳ね返すことができると考えます。
【正気を養う漢方的な基本の養生】
- 規則正しい生活と十分な休養
エネルギー源となる「気(き)」を補い、巡らせることが基本です。睡眠不足や過度なストレスは気の消耗に直結します。夜はしっかり体を休ませ、エネルギーを蓄えましょう。 - 粘膜のバリア機能を強化
ウイルスや細菌は主に鼻や喉の粘膜から侵入します。漢方では、粘膜は「潤い」を好むと考えられています。特に「晴れの国おかやま」は、冬場にかけて空気が乾燥しやすい傾向があります。加湿やこまめな水分補給はもちろん、漢方的なアプローチとしては、体の内側から潤いを生み出す「麦門冬湯(ばくもんどうとう)」のような漢方薬も有効な場合があります。 - 胃腸を整える
漢方では、飲食物から「気」や「血(けつ)」を生み出す「脾(ひ)」(胃腸)の働きを非常に重視します。消化吸収を助けることで、体全体のエネルギーを高め、「正気」を補います。「補中益気湯(ほちゅうえっきとう)」などの漢方薬は、胃腸の働きを助けながら、体力や免疫力を底上げする代表的な処方です。
2. 季節ごとの養生とおすすめ食材(秋・冬編)
季節の「邪気」の特性を知り、それに合わせた対策をとることで、未病を防ぐことができます。
| 季節 | 漢方的な邪気 | 体への影響と対策 | おすすめ食材 |
| 秋 | 燥邪(そうじゃ) | 乾燥により、喉の痛み、空咳、皮膚の乾燥などが起こりやすい。特に「肺」を潤すことが大切。 | 白系の食材: 梨、蓮根、白きくらげ、山芋など |
| 冬 | 寒邪(かんじゃ) | 冷えにより血流が滞り、免疫力が低下しやすい。体を温め、エネルギー(陽気)を蓄える養生を。 | 体を温める食材: 生姜、ネギ、ニラ、ラム肉、温かいスープなど |
3. 「ひきはじめ」に漢方薬を上手に活用する
もし体調を崩してしまった場合、漢方薬は症状の進行を防ぐために、「ひきはじめ」に使うことが特に重要です。症状や体質に合わせて使い分けることで、治癒を早めるサポートをします。
| 症状のタイプ | 漢方的な見方 | おすすめの漢方薬 |
| ゾクゾクと寒気、肩こり、汗が出ていない風邪 | 体に冷え(寒邪)が侵入した状態 | 葛根湯(かっこんとう) |
| 寒気が強く、高熱、関節痛、体力のある方 | 寒気が強く、体の奥まで冷えが入り込んだ状態 | 麻黄湯(まおうとう) |
| 喉の痛み、熱っぽい風邪 | 喉や口から熱(熱邪)が侵入した状態 | 銀翹散(ぎんぎょうさん)など |
| 風邪ではないが、のどの違和感がある | 漢方茶で日常的にケア | 板藍茶(ばんらんちゃ)など |
これらの漢方薬は、症状が体に侵入した初期段階で「邪気」を追い出すことを目的としています。タイミングを逃さずに服用することが大切です。
おわりに:体質に合った漢方で万全の対策を
漢方薬は、同じ感染症でも「一人ひとりの体質や症状の現れ方」に合わせて使い分けることが最大の強みです。
「正気」を高めるための養生はすぐに始められますが、より体質に合った漢方薬を選ぶためには、専門家による診断が必要です。
「なんとなく調子が悪い」と感じたら、それは体が発する大切なサイン。ぜひ一度、漢方の専門家にご相談ください。あなたの「正気」を固め、季節の変わり目を健やかに乗り切るためのサポートをいたします。