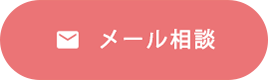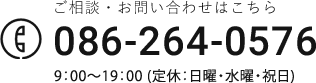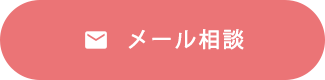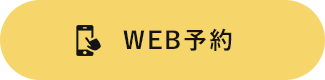IBS(過敏性腸症候群)とは?違いや診断方法・漢方でのアプローチ2025.10.09

IBSと過敏性腸症候群の違いは?
「IBS」という言葉をネットや病院で聞いたことがある方も多いでしょう。
実は、IBS(Irritable Bowel Syndrome)=過敏性腸症候群を指す医学用語で、両者は同じ病気です。
日本語では「過敏性腸症候群」と呼び、英語の略称で「IBS」と表記されます。
そのため、症状や治療法に違いはなく、「IBS=過敏性腸症候群」と覚えておきましょう。
IBS(過敏性腸症候群)の主な症状
IBSは、大腸などに目に見える異常がないにもかかわらず、便通異常や腹部症状が慢性的に起こる病気です。
代表的な症状は次の通りです:
慢性的な腹痛や腹部不快感
下痢や便秘が続く、または両方を繰り返す
ストレスや緊張時に症状が悪化
ガスが溜まりやすく、お腹が張る
朝、外出前にトイレに何度も行きたくなる
IBSは命に関わる病気ではありませんが、生活の質(QOL)を大きく下げる原因になります。
「仕事に遅刻してしまう」「旅行が不安」「外食が楽しめない」といった悩みを抱える方が非常に多いです。
IBSを疑うきっかけになるサイン
「IBSっぽいかもしれない」と思うサインをまとめました。
次の症状が3か月以上続いている場合は、IBSの可能性があります。
特に食後や出勤前など、ストレスの多いタイミングで腹痛や下痢が起こる
便秘と下痢を繰り返す
下痢止めや整腸剤を使っても改善しない
トイレに行くと腹痛が一時的に楽になる
病院の検査では「異常なし」と言われた
これらは、IBSの典型的なパターンです。
ただし、同じ便通異常でも炎症性腸疾患や大腸がんなど別の病気の可能性もあるため、自己判断せず医師に相談することが大切です。
IBSかどうか確かめる方法
IBSは、血液検査やレントゲンで明確に「陽性」「陰性」と判定できる病気ではありません。
診断には、**「除外診断」**という方法が用いられます。
医療機関で行う検査
問診
症状の期間、腹痛と便通の関係、生活習慣を詳しくヒアリング
血液検査・便検査
感染症や炎症が原因でないか確認
大腸内視鏡検査
大腸がんや潰瘍性大腸炎など、器質的な病気を除外
診断基準(ローマⅣ基準)
過去3か月で月1回以上、腹痛が便通と関連しているかどうかを確認
これらを総合して、他の病気が否定されると「IBS」と診断されます。
IBSとストレスの深い関係
IBSの症状は自律神経の乱れやストレスと深く関わっています。
緊張や不安を感じると、交感神経が優位になり腸の動きが乱れ、
下痢や便秘、ガス溜まりなどが悪化します。
このため、薬だけでなく「心と体のバランスを整えるケア」が重要です。
睡眠不足、食生活の乱れ、過度なストレスは、IBSの症状を悪化させる大きな要因です。
西洋医学での治療法
医療機関でのIBS治療は、主に薬物療法が中心です。
下痢型IBS → 下痢止め、腸の動きを整える薬
便秘型IBS → 下剤、腸管運動を促す薬
ガス型IBS → 整腸剤、抗ガス薬
抗うつ薬や抗不安薬(自律神経に働きかける)
症状を一時的に抑える効果はありますが、根本原因であるストレスや体質は改善しにくいという課題があります。
漢方でのIBSアプローチ
IBSは「検査では異常がないのに辛い」という特徴があり、
西洋医学だけでは改善が難しいケースも多く見られます。
漢方は、体質や症状の背景にある「根本原因」を整えることが得意分野です。
特にIBSでは、以下のような状態を考慮して処方を行います。
IBSに多い体質タイプ
気滞タイプ(ストレス過多)
→ イライラ、ガス溜まり、便通が不安定
気虚タイプ(体力不足)
→ 疲れやすい、下痢しやすい、冷え性
寒熱錯雑タイプ(冷えと熱が混在)
→ 下痢と便秘を繰り返す、冷たい飲食で悪化
よく使われる漢方薬例
半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう):下痢型やストレス性胃腸症状に
桂枝加芍薬湯(けいしかしゃくやくとう):ガスやお腹の張りに
加味逍遙散(かみしょうようさん):ストレス過多で便通が乱れるタイプに
補中益気湯(ほちゅうえっきとう):体力低下・疲労による便通異常に
※必ず漢方に詳しい医師や薬剤師に相談しましょう。
自宅でできるセルフケア
IBS改善のためには、日常生活の見直しも不可欠です。
規則正しい睡眠
冷たい飲み物や脂っこい食事を控え
食物繊維を適度に摂る(下痢型は水溶性食物繊維がおすすめ)
深呼吸や軽い運動でストレスを和らげる
トイレを我慢しない
これらを意識するだけでも、症状の安定につながります。
まとめ|「IBSっぽい」と感じたら早めに相談を
IBS=過敏性腸症候群で、両者は同じ病気
腹痛や便通異常が3か月以上続く場合はIBSの可能性あり
他の病気を除外するためにも、まずは消化器内科で検査を
薬だけでなく、体質改善やストレスケアが根本治療に不可欠
漢方は、IBSに多い「自律神経の乱れ」や「腸のバランスの崩れ」を整える力があります。
「検査では異常なしなのに辛い」「薬を飲んでも改善しない」という方は、
一度、漢方薬局や漢方外来での相談を検討してみてください。
執筆者
服部 雄志(国際中医師/漢方専門家)
漢方薬に関する豊富な知識と経験を持ち、不妊治療における漢方相談を多数手がける。
経済的な負担や精神的なストレスを抱える方々に寄り添い、希望を与えるサポートを行っている。
妊活・不妊治療に関する情報発信を行うライター。読者に寄り添った記事を心がけている。
著書に『母になるために大切にしたい妊活の習慣』(WAVE出版)がある。
▼ 不妊治療の経済的なお悩み、ぜひご相談ください ▼